|
TOP > 花火うんちく








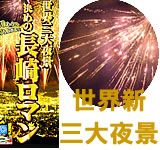











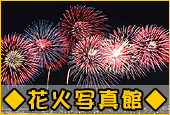

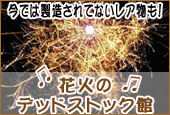
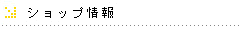
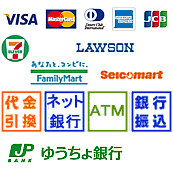
小さな、はかない線香花火
でも、奥深い趣きの変化や、もっと綺麗にみる方法、地域性の違いなど、日本の心を表現する秘密があるんです。
はじまりい~ はじまりい~
牡丹
点火して最初の現象です。
真ん中の大きな丸い玉も「牡丹」のよう。
短い火花が重なり合い、「牡丹」といわれる所以です。
松葉
線香花火の一番激しく、そして美しいとき。
広く飛び散る様は、まるで「松葉」のよう。
明るく輝いています。
柳
次に、柳。火花がしな垂れるように、下に伸びます。
風に舞うかのように
自然に身をまかせるかのように
描いた孤が趣を醸し出します。
ちり菊
最後は、ちり菊
菊の花びらが咲いては散って
咲いては散って
を繰り返し、線香花火の物語の終焉です。
国産の線香花火は、ここからが「長く」いつまでもいつまでも余韻を残して漂います。
長持ちさせる秘密。
それは、先端の部分にあります。
先端には火薬が詰まって、少し膨らんだ部分があります。(その部分を「玉」と呼びます。)
その玉の部分のすぐ上。少しくびれた部分をほんの少し、ひねってください。
締めるイメージです!
それで、随分と持ちが変わってきます。
生まれと持ち方の違い
花火と言えば、夜空に満開に拡がる打上花火!? 打上花火も結構ですが、個人的にはしみじみと楽しむ「線香花火」が大好きです。当然打上花火もいいですが、線香花火は、花火のシメ、夏のシメには欠かせないアイテムです。
一概に「線香花火」と言いましても、「すぼて」と「長手」があります。
あなたは、線香花火っていったら「すぼて」と「長手」どちらを思い浮かべますか?どちらを思い浮かべるかによって、あなたの住んでいる場所がわかるます。
「すぼて」は、手に持つ部分が、藁(わら)でできており、先頭の火薬部分は黒色をしてます。
一方、「長手」は、全体が紙でできており、「こより」のような感じです。
一般に「すぼて」は西日本で多く使用され、逆に「長手」は東日本で使用されているようです。当店は、長崎にありますので、線香花火といったら「すぼて」を連想しますし、やはり「すぼて」の方がよく売れます。余談になりますが、すぼてに慣れ親しんだせいか、やはり私は「すぼて」の方が好きです。
使用方法(持ち方)も違います!
上45度(斜め上)に向け使用すると、火球が落ちにくく長く美しく楽しめます。
下45度(斜め下)に向け使用すると、火球が落ちにくく長く美しく楽しめます。
手持花火「ススキ」「スパーク」「カラーチェンジャー」の違いは?
おもちゃ花火の王道はやはりなんといいましても、「手持花火」ですよね。
でも手持花火の種類には、例えば「5変色ススキ」、「5変色スパーク」や「5変色カラーチェンジャー」など一見、「何がどう違うの?」と感じられると思います。
そこで私の独断と偏見を持って解釈いたしましたので、よろしかったらご覧くださいませ。
「ススキ」が昔ながらの花火という感じです。比較的価格の低く設定されております。また、他の2者に比べて、燃焼時間が長めであり、趣深いしみじみとした火花が出ると思われます。昔の幼い頃を思い出させる花火です。
「パチパチ」花火といったところでしょうか。勢いよく飛び出す火花は圧巻です。ただし、花火の表面に火薬がいっぱい付いており、手で触ると火薬がとれるのが弱点です。スパーク系花火の代表選手「針金スパーク」は、シンプルではありますが、根強いフアンがいらっしゃいます。
上記2者に比べ、比較的新しい花火です。カラーチェンジャーはその名のとおり、火花の変色が大の得意です。10変色は当たり前、20変色、25変色するものまでありますよ。拡がりをもった火花を生じます。
「打上げ玉」の種類
夏の夜空を華麗に彩る花火。今年の夏は、豆知識を仕入れて、話題豊富なあなたになってみませんか。いつもの年の何倍も花火を楽しめるかも。ターマヤー!
観る花火---「打ち上げ玉」
「打ち上げ玉」には、花のように開く「割物」と、星や小さな玉を打ち出す「ポカ物」とがあります。
「割物」は、打ち上げと同時に導火線に火がつき、ほどよいタイミングで導火線の火が割薬に到着すると破裂してその火が星に燃え移って美しく発色します。開き方が1重なのが「菊物」と「牡丹物」、2重なのが「芯物」、3重なのが「八重芯」、4重なのが「三重芯」です。「菊物」は、破裂の中心部から火ぼこりが尾を引いて出て、火ぼこりの先で色が変化するもの。そのうち、星がゆっくり燃えるものを「冠菊」と言います。また、「牡丹物」は、中心部から色のついた星が尾を引かないで飛んでいくものです。
「ポカ物」とは、空の上で玉を「ポカッ」と開かせ、玉の中に詰めた星や細工物を放出する玉で、構造は運動会などの合図用の昼玉と同じです。小さい玉を入れた「小花」、不規則に飛び散る「蜂」、1ヶ所から左右に星が飛んでいく「分砲」、音を出して銀色の火の粉を散らす「銀笛」、星より大き目の仕掛けが放射状に広がって椰子の葉のように見える「椰子」などがあります。
「スターマイン」は、1つの筒の中に玉1~2個と、小さな星になる「ざら玉」を入れ、導火線の長さの違うたくさんの筒をつないで、時間差で連続発射する仕組み。空中へ打ち上げるもののほか、地上や水上で開かせるものもあります。
中国盆は、長崎ならではの行事で、旧暦の7月26日から28火に崇福寺(写真参照)で行われます。盆とはいっても、日本のお盆とは意味合いが違って、いわゆる「施餓鬼(せがき)」であります。
施餓鬼とは、「悪道におちて苦しんでいる亡者(餓鬼)に飲食物を施すという法会(ほうえ)」のこと。つまり、死後も苦しんでいるすべての霊を供養する行事で、自分の先祖を供養とは全く別の行事なのです。その証拠に、華僑の人たちも。8月には中国盆とは別に日本式のお盆の供養をするそうです。
では中国盆をご案内いたしましょう。
盆の7日前には「ハッポン」といって、崇福寺の第1峰門(国宝)と、新地の真中にあるお堂に黄色い紙が張り出されます。これはあくまでも霊魂たちへの告示で、人間へのお知らせではありません。
国宝の本堂に向かって左手にあるのが「三十六軒堂」。これは、霊魂たちが買い物をする「商店街」です。よく見ると、なぜかその中に棺桶屋まであります。
3日目の朝には、十錦菜(せっきんさい)と呼ばれる14種類の精進料理が所狭しと供えられ、夕方になると、豚の頭や鶏でつくった老人の人形など生臭料理も並べられます。
そして、3日目の夜になると紙製の「中国かばん」の中に、紙でつくったいろいろの物が入れられ、冥土の土産として燃やされ、中国盆が終わります。
と思ったら、それから1日置いた旧暦の30日には補施(ぽーせ)という行事があります。これは目や足が不自由で盆に間に合わなかった霊魂のためにお経をあげる行事です。山門から本堂まで足元に竹線香を並べ、霊魂が迷わずに到着するように気配りをします。
霊魂たちを手厚くもてなす中国盆。その独特の雰囲気は日本でもここでしか味わえません。長崎の大切な風物詩の1つです。